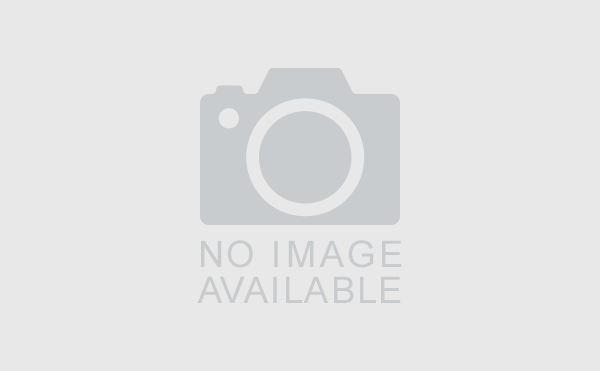各地方自治体(市区町村)の補聴器購入費助成制度について
最近、各地方自治体(市区町村)で補聴器購入のための助成制度が全国各地で広がっています。
今回は、補聴器の助成制度について書かせて頂きたいと思います。
補聴器購入費助成制度について
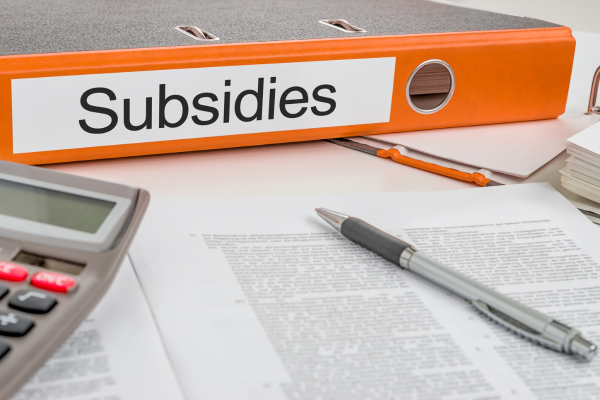
補聴器購入の助成制度は、聴覚障害の手帳をお持ちの方が障害者総合支援に基づき利用できるもの、補聴器相談医の先生の検査・診察により利用ができる『医療費控除の制度』があります※1
近年はそれ以外にも、補聴器購入のための助成制度が少しずつですが増えてきました。
※1 上記の制度の利用には、耳鼻科医の診察が必須となり、一定の要件があります。
近年増加している補聴器購入費助成制度は?

上記に書いてある、聴覚障害の手帳をお持ちの方対象の制度や医療費控除の制度以外のものが、各地方自治体(市区町村)で広がりつつあります。
以下、情報を掲載します※2
※2 2023年6月時点での情報です。
どれくらいの自治体(市区町村)が実施しているか?
全国の市区町村は1747あります。
その中で実施している数は、152です。
新潟県が最も多く、東京都が次いで多いです。
愛知県で助成を実施している自治体
犬山市、稲沢市、大府市、あま市、設楽町※3
※3詳細は、各自治体にお尋ね下さい。
対象となる年齢
各市区町村によって異なりますが、約60%が65歳以上を対象としています。
助成金の限度額

20,000円、30,000円、50,000円を限度額としている自治体が多いです。
補聴器相談医、認定補聴器技能者との関わり


補聴器相談医への受診や認定補聴器技能者(認定補聴器専門店)での購入や調整が要件となっている市区町村は、152あるうちの約20%です。
助成制度を利用しても適切な補聴器の機器種選択や調整がなされていないと箪笥の肥やしになってしまう可能性もあります。
要件になくても、可能ならば補聴器相談医への受診や認定補聴器技能者(認定補聴器専門店)への来店をおすすめ致します。
この記事を書いた人

- あいち補聴器センター言語聴覚士
-
言語聴覚士として勉強した知識を生かして聞こえについての情報を発信していきます!
水泳と走ることが好きです。